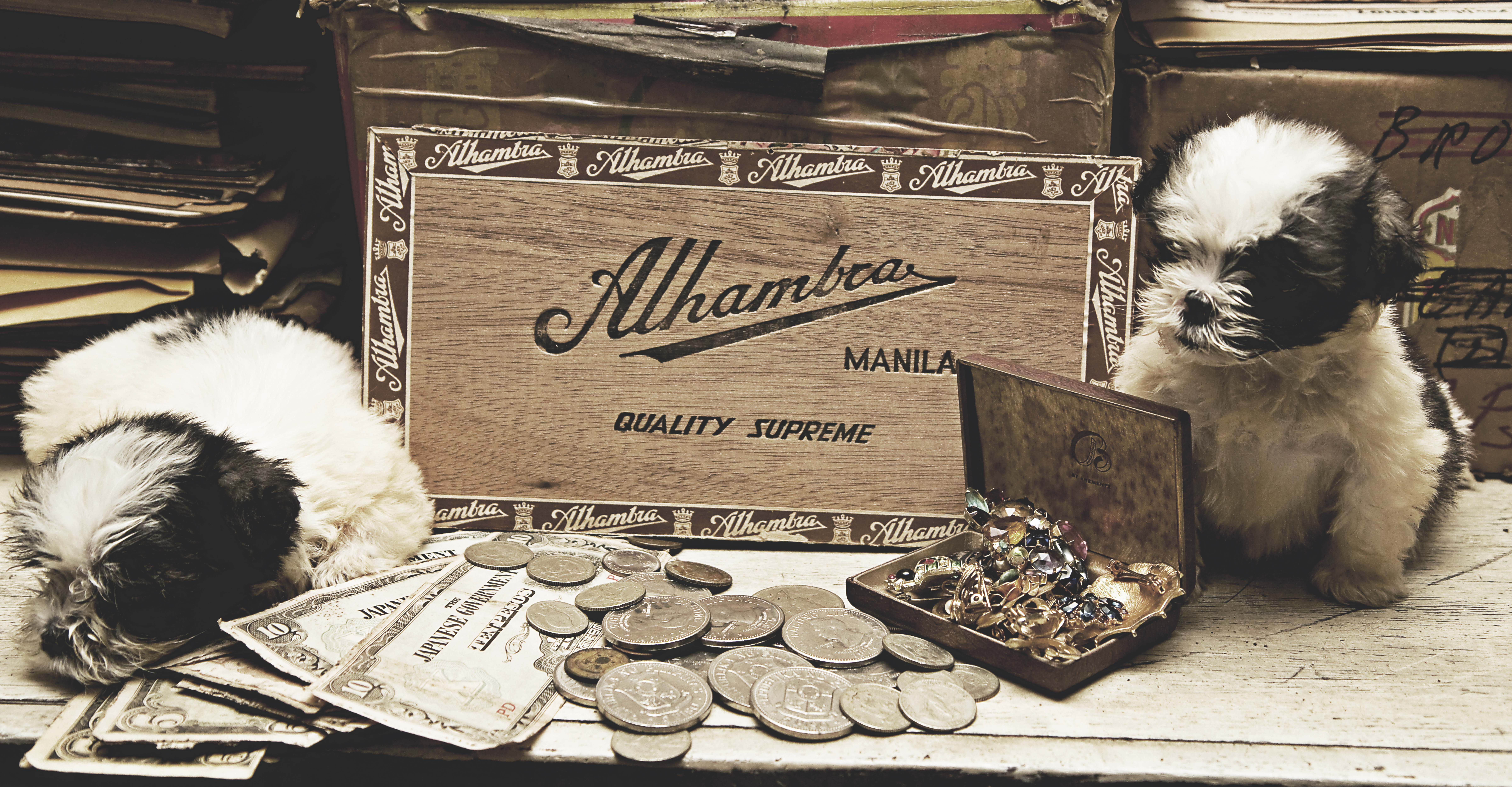はじめに
小規模企業共済という、個人事業主の方、小規模の会社の役員の方のみが自由に入れる退職金制度があるのはご存じでしょうか。
同じような個人で入れる退職金制度にはiDeCoがありますが、入れる人は先にこの制度への加入を検討してよいかと思う制度です。
※個人事業主(共同経営者)と小規模企業の詳細:加入資格 | 小規模企業共済 (smrj.go.jp)
小規模企業共済とはどんな制度?
この制度は国が運営する、個人事業主・会社役員のみが入れる、節税にもなる、退職金制度です。
特徴としては以下のような特徴があります。
- 節税をしながら老後の資金作りになる
- 支払額(拠出額)は自由に設定可能(月々1,000円~70,000円、年払い、月払い)
- 最終的にもらえる退職金(共済金)は、
一括で全額もらうことも、期間に応じて分割でもらうことも可能 - 支払った累計の額(掛金拠出額)に応じて低金利で借り入れも可能
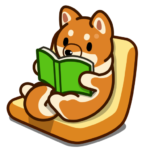
個人事業主の人は、サラリーマンのように会社から退職金がもらえるわけではないのでありがたいね
小規模企業共済の特徴について
①節税をしながら老後の資金作りになる
基本的には毎年支払った額が運用されて、最終的に運用額が退職時に返還される制度です。
単純な運用率だけでいうとそこまで高くないのですが、節税分と考慮すると、ただ貯金するより、お得になる計算です。
例えば、以下の場合は実質返礼率は170%以上にもなります。
(前提)
・40歳の人が65歳まで、25年間加入
・月々7万円(年間84万円)掛金支払
・課税所得600万円
(結果)
支払額(掛金) 合計 :2,100万円
節税額 合計 : 639万円(※1)
実質支払額 合計 :1,431万円
退職金(共済金) :2,534万円(実質支払額の170%超)
(※1)639万円=年間節税額25.5万円(※2)×25年間
(※2)25.5万円=支払額84万円×税率30%程度(所得税20%程度+住民税10%)
上記の節税額がなぜ発生するかというと、
この小規模企業共済の支払額は、所得税の「所得控除」ができるからです。
節税額は、『支払額 ×(所得税税率+住民税率)』になります。
住民税率は10%程度ですが、所得税率はその人の稼ぎによって段階的に上がっていくので、所得が高い人ほど節税額は高くなります。
所得税と住民税の税率の合計が30%程度の人であれば、
年間84万円(月7万円)支払っても、30%程度分の25.5万円程度税金が減るので、
実質的には年間58.5万円程度(1月あたり5万弱)の支払額で済むという計算です。
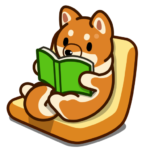
今はホームページ上で、どれくらい払えば、どれくらい返ってくるかシミュレーションもできるので、いろいろ検討してみよう
小規模企業共済制度 加入シミュレーション:試算条件の入力|独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)
また、最終的に受け取る退職金(共済金)は、
所得税法上、退職所得か、雑所得(公的年金等に係る雑所得)の区分として受け取ることができます。
受取時には税金がかかってしまいますが、
この退職所得と、雑所得(公的年金等に係る雑所得)の区分の税率や税金計算方法は、
現状、他の区分の収入(給料、譲渡、事業所得等)よりも優遇されているので、
自力で退職資金を作る場合よりも手残りが多くなる可能性が高いです。
②支払額は自由に設定可能
掛金については、自由に設定が可能で、年払い、月払いの選択が可能です。
一度設定した掛金額も増額、減額の変更も可能です。
なお、減額した場合は、減額分、運用される金額が減少してしまうことには注意しましょう。
| 掛金月額 | 1,000円~70,000円の範囲内で、500円単位で設定できます。 |
|---|---|
| 納付方法 | 掛金の納付方法は、口座振替(共済契約者ご本人の個人名義の預金口座)となります。 毎月納付する「月払い」、あらかじめ届け出た月(年1回)に12か月分の掛金を納付する「年払い」、またはあらかじめ届け出た月(年2回)に6か月分の掛金を納付する「半年払い」から選択できます。 |
| 口座 振替日 | 毎月18日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
小規模企業共済の掛金 | 小規模企業共済 (smrj.go.jp)
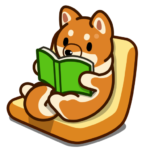
掛金はなるべく減額しないようにしたほうがよいかな
12月にまとめて年払いする形式にして、1年の稼ぎの状況を見て支払額を決めるのもよいかもしれない
③退職金(共済金)の受け取り方
共済金は、基本的には以下の場合等により受け取ることができます。
・個人事業を廃業した場合
・65歳以上かつ掛金納付月数180か月以上となった場合
・任意で解約した場合 等
その他にもいろいろなケースがありますが、
一般的には、各ケースごとに定められた必要書類を集め、共済金を受け取るための請求書を作成し、口座を指定して金融機関に承認をもらい、資料提出という流れになります。

共済金等請求・解約 | 小規模企業共済 (smrj.go.jp)
⑤低金利の借入制度
条件はありますが、
今まで支払った掛金分等がすぐに借り入れができるので、
手元資金がなくなってしまうリスクに対しても備えることができます。
例えば、一般貸付制度であれば、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借り入れ(利率1.5%)をすることができます。
以下のパターンの貸付制度があるため、急なお金が必要となった際に利用を検討することができます。
・一般貸付(事業資金)
・緊急経営安定貸付
・傷病災害時貸付(病気の時など)
・福祉対応貸付
・創業転業時・新規事業展開等貸付
・事業承継貸付
・廃業準備貸付
同じように個人的に入れる退職金制度で、iDeCoがありますが、iDeCoは積み立てた資産は引き出しができなくなるので、急に資金が必要になったときに対応できない可能性があります。
その点と比較すると柔軟性がある制度かと思います。
共済契約者貸付 | 小規模企業共済 (smrj.go.jp)
小規模企業共済のデメリット
いくつか注意点もあるので以下の点は考慮が必要です。
- 12か月未満は掛け捨てリスクがある
- 任意解約の場合、加入して20年間未満は元本割れとなる
- 受取時の退職金の受け取り方法については税金がかかるので、受け取り方についてシミュレーション等検討が必要
①12か月未満は掛け捨てリスクがある
掛金納付月数が、12カ月未満の場合は、
準共済金(法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合)、
解約手当金(任意解約や、掛金を12カ月以上滞納した時の機構解約)
等は受け取ることができません。
②任意解約の場合、加入して20年間未満は元本割れとなる
掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ってしまい、元本割れしてしまいます。
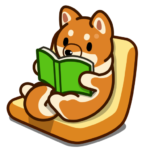
基本的には長く加入できる人向けということかな
③受取時の税金シミュレーションが必要
最終的に退職金(共済金)として受け取る場合、一括か分割で受け取ることができます(65歳以上の場合)。
一括か、分割受け取りかで、所得税上分類が異なり、適用される税金も変わってくるので、
その時の資金の必要性と、税金支払い額を考慮して受け取り方を考えることがベターかと思います。
<所得税上の分類>
①一括受取 ⇒ 退職所得
②分割受取 ⇒ 雑所得(公的年金等の雑所得)
また、65歳未満で任意解約をしてしまうと、解約手当金は税法上、一時所得として取り扱われてしまい、税務上優遇された税率でなくなってしまうため、大きく受け取れる金額が減ってしまう可能性があるため注意しましょう。
小規模企業共済への入り方
加入申込み手続は、
中小企業基盤整備機構のオンラインページから申し込むか、
最寄りの商工会、商工会議所等の委託団体又は金融機関等の窓口で申込み手続ができます。
加入手続き | 小規模企業共済 (smrj.go.jp)
オンラインの場合は、以下のような手順になります。
①小規模企業共済オンライン手続きポータルページよりメールアドレス登録
②マイナンバーカードの読み取り
③契約情報入力、申し込み入力
なお、書類提出の場合は、申込書を入手して、必要事項を記入の上、委託団体又は金融機関等に提出する流れになります。
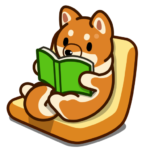
マイナンバーカード(+スマホ)があれば、オンライン手続きができるので、そちらのほうが楽かもしれない
まとめ
今回は小規模企業共済について紹介しました。
しっかり長期間加入できれば、メリットがある制度かと思いますので、税理士等にも相談して加入を検討することをオススメします。